|
|
 ある対談に出席していたホルヘ・バルダーノがクライフに質問する。 だが多くの監督にとってそれは納得のいかないアイデアとなる。70mから75mもある横幅を利用して攻めてくる相手チームの攻撃を防ぐには、最低4人のディフェンスが必要だと考える監督が一般的だ。4人では不安だから5人のディフェンスが必要と考える監督さえいる。だがクライフは3人でじゅうぶんだという。そしてディフェンスで削った1人をデランテーロにまわす。いわゆる3−4−3システムだ。これなら1人余計に相手ゴールに近い選手が増えるし、中盤から上でよりボールを支配することも可能となる。その結果、自陣のゴールからより遠くにボールがあることになる。 クライフにとって、この3−4−3システムの有効性はすでにアヤックスで立証済みだった。新人監督としてアヤックスを率いてカップ戦を2回、レコパのタイトルを1回とっていた。だが多くの地元メディアやバルセロニスタが心配したことは、オランダリーグと違い競争の激しいスペインリーグでそのシステムが通用するかどうかということだった。ちなみにこの3人ディフェンスは2002年の韓国・日本ワールドカップで多く見られた3人ディフェンス(3人セントラール)+左右のサイド選手をおくシステムとは異なる。ここでいう3人ディフェンスとは一人のセントラールと左右のサイドバック選手をおくスタイルだ。したがってバンガール第二次政権で見られるカリレーロというポジションも存在しない。 もちろんこの3−4−3システムはクライフが発明したものではない。アヤックスを中心とするオランダの名門クラブがよく起用していたシステムだ。だがより正確に言うならば、常にこのシステムを優先的に使っていたわけではない。例えばアヤックスにしても、相手チームがはっきりと実力的に劣る相手だったり、どうしても攻撃的な戦法を必要とする場合のみ使用していた。しかもテクニックや体力的にも優れている選手が揃って初めて有効となるシステムであった。 クライフの偉大なところは、そういう条件を備えていない選手たちでもそのシステムが生きるということを証明したことだろう。バルサは歴史的に「体力面の強さ」を持つ選手を基盤として戦ってきたチームではないし、コパ・デ・ヨーロッパを勝利したバルサの選手にしてもそうだった。グアルディオーラやラウドゥルップなどに、相手を突き飛ばすようなパワーがあるとはいえない。しかもテクニック的にみてもフェレールやサリーナス、そしてチキやバケーロ、フアン・カルロスなどが特に優れていたとはとても言えない。あのアヤックスの最盛期にいた選手たちとは、テクニック的にも体力的にも劣る選手が多いバルサだった。
攻撃面はどうだろうか。特徴的なのは左右に大きく開いたエストレーモ(7番・11番)の存在だ。左右に大きく開くことにより、相手サイドバックの選手も大きく開くことを要求される。したがって相手ディフェンスが4人の場合は2人が真ん中に残され、5人の場合は3人が中央ラインを守ることになる。クライフバルサの最初の2、3年間、プンタ(9番)は後ろに下がり気味に位置するのが普通となっていた。いわゆる「見せかけのプンタ」としてラウドゥルップとバケーロがその役目をしている。下がり気味のプンタを相手に、中央ディフェンスの選手は彼らをマークするために前に上がることはできない。したがって、具体的にマークする選手が存在することなく中央ラインにたたずむことになる。つまり左右のサイドバック選手はそれぞれエストレーモの影となり大きく開かされ、中央ラインディフェンスはマークする選手をみつけられることなしに守りに入らされることになる。 ではこのような配置において誰がゴールを決めるのか。基本的アイデアは中盤の選手だ。ボールを支配し、ボールを回しながら、ラウドゥルップやバケーロは下がり気味でチャンスを狙う。そしてスキをみて上がってくるアモールやエウセビオ、あるいはチキ。もちろんエストレーモのストイチコフやゴイコがスピードをいかしてゴールに飛び込むパターンを忘れてはならない。彼らにクーマンやグアルディオラ、そしてラウドゥルップからのパスが送られてくる。中央ラインを守っているディフェンス陣は、最終的には突然上がってくる中盤の選手に対応しなくてはならなくなる。もちろん相手中盤の選手も、バルサ選手の上がりに注意を払わなくてはならないので、なかなか攻撃に手が回らない。 いずれにしてもこのアイデアにどうしても欠かせないのは左右に大きく開いたエストレーモといえる。それもほぼ白線を踏むほどに左右に開かれたエストレーモだ。これはクライフがくどいほどに固執することでもある。そうでなければリネッカーやサリーナスという「9番」の選手をエストレーモに起用することの説明がつかない。エストレーモ専門の選手が存在しなかった初期のクライフバルサにおいて、スピードのある選手を優先的にエストレーモに配置しなければならない台所事情があった。当人たちはもとより、多くのバルセロニスタにしても納得のいかない彼らのエストレーモ起用ではあったが、その後のシステムの継続性を見ていくことで納得させられていく。と同時に、クライフバルサの試合を見ていくに従いエストレーモの重要性をバルセロニスタも学んでいったのだ。 さて中盤の選手のことを忘れてはならない。ディフェンス面や攻撃面で重要な役割を果たすのがこの中盤だ。彼らには二つの使命がある。一つはボール支配とコントロール、そしてもう一つはカウンターアタックを防ぐための的確なポジショニングとプレッシャーだ。それの最高の形として示されるのは、ワンタッチボールによる左へ右へ、上へ下への素速いパスとなる。ボール支配とコントロール能力、そして的確なポジショニングがあって初めて生まれるものだ。アルゼンチンの名将メノッティが言う「攻撃をするのに焦っては成功しない。ゴールはほんのチョットした瞬間に生まれる」という言葉を待つまでもなく、ボールを支配し、コントロールし、それぞれの選手が的確なポジションについて一瞬のスキを狙った攻撃でゴールが生まれる。 |
|
|

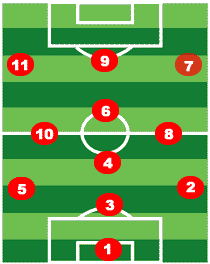 クライフがこれまでおこなってきたディフェンス面を見てみよう。まず3人のディフェンス(2番・3番・5番)が自陣キーパーとの間に大きなスペースが生まれることを覚悟で前に出る。通常この3人のうち2人(2番・5番)は相手デランテーロのマークに入る。そして残った一人がリベーロ(3番)となって守備の要の仕事をする。ここで要求されることはポジショニングの正確さと、中盤から上にいる選手たちによる援助だ。もしそれぞれが適切なポジションをとり、各選手が相手選手にプレッシャーをかけられれば、思い通りにボールを出すことを防ぐことができる。だがこのシステムは、中盤以下の選手に極限までの集中力を要求することになる。なぜなら一人でも自分の場所がわからなかったり、リラックスした選手がいたら簡単に突破される可能性があるからだ。
クライフがこれまでおこなってきたディフェンス面を見てみよう。まず3人のディフェンス(2番・3番・5番)が自陣キーパーとの間に大きなスペースが生まれることを覚悟で前に出る。通常この3人のうち2人(2番・5番)は相手デランテーロのマークに入る。そして残った一人がリベーロ(3番)となって守備の要の仕事をする。ここで要求されることはポジショニングの正確さと、中盤から上にいる選手たちによる援助だ。もしそれぞれが適切なポジションをとり、各選手が相手選手にプレッシャーをかけられれば、思い通りにボールを出すことを防ぐことができる。だがこのシステムは、中盤以下の選手に極限までの集中力を要求することになる。なぜなら一人でも自分の場所がわからなかったり、リラックスした選手がいたら簡単に突破される可能性があるからだ。